ロードバイクに乗り始めると、必ず耳にする言葉がケイデンスです。ケイデンスとは、1分間あたりのペダル回転数を示す指標であり、単位はrpm(revolutions per minute)で表されます。サイクルコンピューターに表示されるこの数値は、単なる回転速度を示すだけではなく、実はライダーの身体にかかる負荷の質を大きく左右する重要なパラメータなのです。初心者からベテランまで、多くのサイクリストが「90rpmが理想」という言葉を聞いたことがあるでしょう。しかし、実際のところ、最適なケイデンスは個人の体質や走行シーン、目的によって大きく異なります。高いケイデンスで軽いギアを素早く回転させるスタイルと、低いケイデンスで重いギアを力強く踏み込むスタイルには、それぞれ明確なメリットとデメリットが存在します。どちらが優れているという単純な話ではなく、両者の特性を深く理解し、状況に応じて使い分けることこそが、真のサイクリングスキルと言えるでしょう。本記事では、ロードバイクのケイデンスについて、低い場合と高い場合のそれぞれの利点と欠点を、生理学的な視点や実戦的な戦略を交えながら、包括的に解説していきます。

ケイデンスの基礎:パワーとトルクの関係性
ロードバイクのパフォーマンスを理解する上で、まず押さえておくべきはパワー、トルク、ケイデンスの三つの要素がどのように関連しているかという点です。物理的には、パワー(ワット)はトルク(ペダルに加える回転力)とケイデンス(回転速度)の掛け算で表されます。つまり、同じパワー出力を得るためには、高いトルクで低いケイデンスを選択することも、低いトルクで高いケイデンスを選択することも可能なのです。たとえば、300ワットの出力を得るために、重いギアをゆっくり回すことも、軽いギアを素早く回すことも理論的には同じ結果をもたらします。
しかし、この選択は決して単純なものではありません。なぜなら、トルクとケイデンスの組み合わせによって、身体にかかる負荷の種類が根本的に変わってくるからです。高トルク・低ケイデンスのペダリングは筋骨格系に大きなストレスをかけ、筋力と筋持久力を要求します。一方、低トルク・高ケイデンスのペダリングは心肺系に負荷をかけ、酸素供給能力と神経筋協調性を必要とします。どちらを選ぶかは、ライダーの身体特性、トレーニング状態、そして走行状況によって決まります。
この根本的な選択が、低ケイデンス派(トルク派、マッシャー)と高ケイデンス派(回転派、スピナー)という二つの異なるペダリングスタイルを生み出しました。それぞれのスタイルには独自の哲学と戦略があり、プロのレース現場でも長年にわたって議論が続けられてきたテーマです。次の章では、この二つのスタイルを詳細に比較し、それぞれのメリットとデメリットを掘り下げていきます。
高ケイデンススタイルのメリットとデメリット
高ケイデンススタイルとは、一般的に80rpm以上、特に熟練したサイクリストであれば90~100rpm以上の回転数を維持しながら走行するスタイルを指します。このスタイルは軽めのギアを選択し、ペダルを素早く回転させることで推進力を得る方法です。プロの世界では、かつてランス・アームストロングが山岳ステージでも105~110rpmという驚異的な高ケイデンスを維持し、ライバルたちを圧倒したことで有名になりました。また、クリス・フルームも同様の高ケイデンス戦略で複数回のツール・ド・フランス優勝を果たしています。
高ケイデンスの主なメリット
高ケイデンススタイルの最大のメリットは、筋肉への負担を軽減し、持久力を向上させることができる点です。ペダル1回転あたりに必要な力が小さいため、筋線維へのダメージが少なく、長時間のライドでも筋肉が疲労しにくくなります。特に、人間の筋肉には大きく分けて二つのタイプがあり、持久力に優れた遅筋(タイプI線維)と、瞬発力に優れた速筋(タイプII線維)が存在します。高ケイデンスでは主に遅筋が使われるため、疲労しにくく、長距離のライドやグランフォンドのようなイベントに最適です。
また、高ケイデンスは加速性と反応性に優れています。すでにペダルが高速で回転している状態からさらにスピードを上げるのは、低速から加速するよりも格段に容易です。このため、集団走行中の急な加速や、アタックへの対応、起伏のある地形での走行において大きなアドバンテージとなります。レースシーンでは、高ケイデンスライダーは戦術的に柔軟であり、状況の変化に即座に対応できる能力を持っています。
さらに、高ケイデンススタイルは心肺系に負荷を集中させるという特徴があります。心臓と肺は筋肉に比べて回復が早く、高強度の努力からも比較的短時間で立ち直ることができます。筋肉が深刻なダメージを受けると回復に数日かかることもありますが、心肺系は数時間から一晩で大幅に回復します。このため、複数日にわたるツーリングやステージレースにおいて、高ケイデンススタイルは疲労の蓄積を抑える有効な戦略となるのです。
高ケイデンスの主なデメリット
一方で、高ケイデンススタイルには無視できないデメリットも存在します。最も顕著なのは心肺系への負荷が高いという点です。ペダルを高速で回転させるということは、筋肉が毎分80回、90回、あるいは100回以上も収縮と弛緩を繰り返すことを意味します。この高頻度の筋収縮を支えるためには、大量の酸素を継続的に供給しなければならず、心拍数が上昇し、呼吸も激しくなります。同じパワー出力であっても、高ケイデンスのほうが心拍数が高くなる傾向があるため、心肺機能が未熟なライダーにとっては苦しく感じられることがあります。
また、高ケイデンスを効率的に維持するには高度な神経筋協調性が必要です。90rpm以上で滑らかにペダルを回し続けるには、体幹の安定性と、脚の筋肉を正確なタイミングで協調させる能力が求められます。初心者がいきなり高ケイデンスで走ろうとすると、サドルの上で身体が跳ねてしまい、エネルギーの無駄が生じます。この「バウンシング」は、推進力に寄与しない上下動のエネルギーロスであり、効率を大きく低下させます。高ケイデンスを武器にするには、体幹トレーニングと専用のペダリングドリルを通じて、神経系を鍛える必要があるのです。
さらに、技術的に未熟な状態で高ケイデンスを試みると、パワーの伝達効率が低下するリスクがあります。ペダルストロークの全周にわたって均等に力を加えることができなければ、いくら速く回しても前に進む力は小さくなってしまいます。特にペダルストロークの上死点と下死点付近では、力の加え方が難しく、この部分が「デッドスポット」となりがちです。高ケイデンスでデッドスポットが大きいと、見た目は速く回っているように見えても、実際の推進力は期待したほど得られないという事態に陥ります。
低ケイデンススタイルのメリットとデメリット
低ケイデンススタイルとは、一般的に60~70rpm程度、あるいはそれ以下の回転数で、重めのギアを力強く踏み込んで走行するスタイルです。このスタイルは筋力に優れたライダーに好まれる傾向があり、かつてのプロサイクリストであるヤン・ウルリッヒが代表的な例として知られています。彼は平地や登坂において、比較的低めのケイデンスで大きなギアを回し、圧倒的なパワーを発揮していました。
低ケイデンスの主なメリット
低ケイデンススタイルの最大のメリットは、高い速度を維持しやすいという点です。筋力が十分にあるライダーであれば、重いギアを一定のリズムで回し続けることで、特に平坦路や緩やかな下り坂において非常に高い速度を維持することができます。慣性を活かしながら安定したペースで巡航できるため、風の影響が少ない状況では効率的に距離を稼ぐことが可能です。
また、低ケイデンススタイルは心肺系への負担が比較的軽いという特徴があります。ペダルの回転数が少ないということは、筋肉の収縮頻度も少ないため、酸素の消費ペースが抑えられます。同じパワー出力でも、低ケイデンスのほうが心拍数や呼吸数が低く抑えられる傾向があり、心肺機能に制約があるライダーにとっては楽に感じられることがあります。運動が筋肉主導であるため、心臓や肺への即座の負担は高ケイデンスよりも小さく感じられるのです。
低ケイデンスの主なデメリット
しかし、低ケイデンススタイルには重大なデメリットがあります。最も深刻なのは筋肉の急速な疲労です。重いギアを回すということは、ペダル1回転ごとに非常に大きな力を筋肉に要求することを意味します。この高い負荷は、筋肉内のグリコーゲン(糖質のエネルギー源)を急速に消費し、同時に筋線維に微細な損傷を与えます。さらに、乳酸などの代謝副産物が筋肉内に蓄積しやすくなり、いわゆる「脚がパンパンになる」状態を引き起こします。この筋疲労は回復に時間がかかるため、長距離ライドの後半では著しくパフォーマンスが低下してしまいます。
また、低ケイデンススタイルは加速性や対応力に欠けるという戦術的な弱点があります。重いギアを低速で回している状態から急加速しようとすると、大きな慣性を克服しなければならず、非常に大きな筋力とエネルギーを消費します。このため、集団走行中のアタックや、勾配の急変への対応が遅れがちになります。レースシーンでは、低ケイデンスライダーは高ケイデンスライダーの連続的な仕掛けに対して防戦一方になりやすく、最終的に脚を使い果たしてしまうリスクが高まります。
さらに深刻なのは、怪我のリスクが高いという点です。低ケイデンスでは、ペダルストロークごとに膝や腱、筋肉に非常に高いピーク荷重がかかります。特に膝蓋腱や膝関節の軟骨には継続的なストレスが加わり、長期的には慢性的なオーバーユース障害を引き起こす可能性が高まります。膝の痛みはサイクリストにとって最も一般的な悩みの一つですが、その多くは過度に重いギアを使用することに起因しています。
生理学的視点から見るケイデンスの選択
ケイデンスの選択が身体に与える影響を深く理解するためには、筋線維のタイプと、エネルギー代謝のメカニズムを知ることが重要です。人間の骨格筋は、主に遅筋線維(タイプI)と速筋線維(タイプII)の二種類の筋線維で構成されています。
遅筋線維は持久力に特化しており、酸素を使った有酸素代謝によってエネルギーを生成します。この代謝プロセスは効率が良く、長時間にわたって持続可能です。しかし、発揮できる力は比較的小さく、収縮速度も遅いという特性があります。一方、速筋線維は瞬発力に特化しており、酸素を必要としない無酸素代謝によって強力な力を短時間で発揮できます。しかし、この代謝プロセスは筋肉内のグリコーゲンを急速に消費し、乳酸などの疲労物質を蓄積させるため、長時間の持続は困難です。
ケイデンスは、これらの筋線維のどちらを主に使うかを決定するスイッチのような役割を果たします。高ケイデンス・低トルクのペダリングでは、1回のペダルストロークに必要な力が小さいため、遅筋線維だけで十分に対応できます。このため、疲労しにくい持久的な運動となります。逆に、低ケイデンス・高トルクのペダリングでは、1回のペダルストロークに大きな力が必要となるため、速筋線維を動員せざるを得なくなります。速筋線維の動員は、短時間で強力なパワーを発揮できる反面、急速なエネルギー消費と疲労物質の蓄積を招くのです。
効率の逆説:なぜ60rpmが最適ではないのか
興味深いことに、多くの生理学的研究では、人間の身体が最も代謝効率が良いケイデンスは約60rpm前後だとされています。つまり、同じパワーを出すために消費する酸素量が最も少ないのは60rpm付近なのです。それにもかかわらず、なぜ経験豊富なサイクリストやプロ選手のほとんどが80~100rpmという、より高いケイデンスを好むのでしょうか。
この一見矛盾した現象の答えは、代謝効率と持続可能性は別物であるという点にあります。60rpmで走行する場合、確かに酸素消費量は最小化されますが、そのためには1回のペダルストロークごとに非常に高いトルクを発揮しなければなりません。研究によれば、筋肉の収縮力が最大筋力の約30%を超えると、筋肉内の血管が圧迫され、血流が制限されることが分かっています。
血流が制限されると、二つの致命的な問題が発生します。一つは、筋肉に酸素と栄養が十分に供給されなくなることです。もう一つは、筋肉で生成された乳酸や水素イオンなどの代謝副産物が筋肉内に滞留し、排出されなくなることです。この結果、筋肉内が酸性化し、筋疲労が急激に進行します。脳はこの状態を「危険」と判断し、パワー出力を強制的に低下させるよう命令を出します。これが、低ケイデンスでは「脚が動かなくなる」感覚の正体です。
一方、80~90rpmというやや高めのケイデンスでは、酸素消費量は若干増加しますが、1回のペダルストロークに必要なトルクは大幅に低下します。これにより、筋肉内の血流が維持され、酸素と栄養の供給、そして代謝副産物の排出がスムーズに行われます。サイクリストは、より高い心肺系の負荷を受け入れることで、筋肉の早期疲労を防ぎ、より長時間にわたって高いパフォーマンスを維持できるのです。これは、車のエンジンを燃費重視のエコモードで走らせるか、持続的な高速走行を可能にするパワーモードで走らせるかの違いに似ています。
プロのペロトン(集団)が長時間のレースで平均84~88rpmという特定の範囲に収束するのは、偶然ではありません。これは、代謝効率、筋肉疲労、心肺負荷という三つの要素の最適なバランスポイントを、経験的に発見した結果なのです。
ケイデンスの実践的な使い分け戦略
ケイデンスの科学を理解したところで、次に重要なのは、その知識を実際のライディングにどう活かすかという点です。最適なケイデンスは、走行状況、地形、ライドの目的によって大きく変わります。万能な単一の数値は存在せず、状況に応じて柔軟に使い分けることが求められます。
平坦路での巡航
平坦な道路を一定のペースで巡航する場合、多くのサイクリストにとっての「ホームベース」となるケイデンスは80~100rpmの範囲です。初心者であれば65~80rpm程度から始め、経験を積むにつれて徐々に高めていくのが理想的です。この範囲では、筋肉への負担と心肺系への負担がバランスよく分散され、長時間にわたって持続可能なペースを維持できます。ギアチェンジを頻繁に行い、風や微妙な勾配の変化に対してもケイデンスが大きく変動しないよう調整することが重要です。
登坂(ヒルクライム)
登坂時には、重力に逆らって進むため、自然とケイデンスは低下します。しかし、ここで重要なのは、ケイデンスが極端に低くなりすぎないよう、積極的にギアを軽くすることです。長い登坂では、70~80rpmを目標にギアを選択するのが望ましいでしょう。急勾配では60rpm台に落ちることもありますが、60rpmを下回る状態が長く続くと、筋肉への負担が急激に増し、途中でパワーダウンしてしまいます。
「登りは筋力で押し上げる」という考え方は、短い坂では有効ですが、長い峠道では逆効果です。プロ選手が山岳ステージで高ケイデンスを維持するのは、筋肉を温存し、頂上まで持続可能なペースを保つための戦略なのです。クリス・フルームが2015年のツール・ド・フランスで、40分以上にわたって97rpmという高ケイデンスを維持し続けたのは、その典型例です。
スプリントとアタック
短時間で最大のパワーを発揮するスプリントやアタックでは、100~120rpm以上の非常に高いケイデンスが必要になります。速筋線維を最大限に動員し、爆発的な加速を得るには、筋肉を最も速い速度で収縮させる必要があります。トップスプリンターたちは、ゴール前の数百メートルで瞬間的に120rpm以上まで回転数を上げ、時速70km近い速度に到達します。このような超高ケイデンスを実現するには、日頃からの神経筋トレーニングが不可欠です。
タイムトライアル
タイムトライアルは、一定距離を可能な限り速く走るための競技であり、持続可能な最大パワーを維持することが求められます。多くのトップ選手は、90~105rpmの範囲でタイムトライアルを走ります。この範囲は、乳酸閾値付近の高強度を維持しながらも、筋肉への過度なトルクを避けることができる絶妙なバランスポイントです。グレッグ・レモンが1989年のツール・ド・フランス最終日のタイムトライアルで100rpmを維持し、わずか8秒差で総合優勝を勝ち取ったのは、この戦略の有効性を示す歴史的な事例です。
長距離ライドとトライアスロン
グランフォンドや100km超のロングライドでは、筋肉の温存が最優先事項となります。できるだけ高め(85~95rpm程度)のケイデンスを維持することで、筋肉へのダメージを最小限に抑え、ライド後半でも十分なパワーを残すことができます。
トライアスロンでは、さらに特殊な戦略が求められます。バイクパートの後にランニングが控えているため、バイクでの筋肉ダメージを極力避ける必要があります。多くのトップトライアスリートは、通常のロードレースよりもやや高めのケイデンスでバイクパートを走り、脚の筋線維へのダメージを抑えます。研究では、バイクパートを高ケイデンスで終えたアスリートのほうが、ランパート序盤のペースが速いことが示されています。
ケイデンス能力を高めるトレーニング方法
理想的なケイデンスを理解しても、実際にそれを実行できなければ意味がありません。幅広いケイデンスレンジを効率的に使いこなすには、体系的なトレーニングが必要です。
体幹トレーニングの重要性
高ケイデンスを安定して維持するためには、強固な体幹が不可欠です。体幹が弱いと、ペダルを速く回そうとした際に上半身が揺れ、サドルの上で身体が跳ねてしまいます。この無駄な動きはエネルギーロスであり、推進力に全く貢献しません。
自転車を降りた状態でのコアトレーニングとして、プランク、サイドプランク、バードドッグ、グルートブリッジなどが効果的です。これらのエクササイズは、骨盤と脊柱を安定させる深層筋を鍛え、ペダリング時の土台を強化します。週に2~3回、各エクササイズを30秒~1分間、3セット程度行うことで、顕著な効果が得られます。
高ケイデンススピンアップドリル
このドリルは、神経筋系を鍛え、高回転でも滑らかにペダルを回せるようになるためのトレーニングです。
平坦な道路またはインドアトレーナーで、非常に軽いギアを選択します。30~60秒かけて徐々にケイデンスを上げていき、サドルの上で腰が跳ね始めるポイントまで加速します。跳ね始めたら、わずかにケイデンスを落として、跳ねない最高速度を見つけます。その状態を20~30秒間維持し、上半身と骨盤はリラックスさせたまま、脚だけを動かすことに集中します。数分の休憩を挟んで、これを5~10回繰り返します。
最初は90rpm程度で跳ねてしまうかもしれませんが、継続することで100rpm、110rpm、さらにそれ以上でも滑らかに回せるようになります。
片足ペダリング(シングルレッグドリル)
このドリルは、ペダルストロークの「デッドスポット」を解消し、全周にわたって均等に力を加えられるようにするための最も効果的な練習方法です。
インドアトレーナー、または安全な平坦路で、片足をペダルから外し、もう一方の足だけでペダルを回します。30~90秒間、片足だけでペダリングを続けます。この際、ペダルストロークの下死点で足を後方に引く動作(泥を削ぐような動き)と、上死点で足を前方に押し出す動作を意識します。通常は踏み込みだけで済んでいた動作が、片足だけでは全周をカバーしなければならないため、ハムストリングスや腸腰筋といった普段使われにくい筋肉が強制的に動員されます。
左右それぞれ数セット行うことで、両足でのペダリング時にも、より円滑で効率的なストロークが身につきます。
低ケイデンス・高トルクトレーニング(SFR)
SFR(Slow Frequency Revolutions)は、低速・高負荷でペダルを回すことで、ペダルストローク全体に力を加える技術と、筋力を向上させるドリルです。
緩やかな登り坂、またはインドアトレーナーの負荷を上げた状態で、通常よりも重いギアを選択します。ケイデンスを40~60rpmまで落とし、中程度から高めの強度(FTPの70~90%程度)で、3~15分間のインターバルを行います。この際、上半身は動かさず、体幹を固定したまま、ペダルに円を描くように均等に力を加え続けることに集中します。
このドリルの目的は、単に筋力を増やすことではなく、高負荷の状態でも滑らかなペダルストロークを維持する神経筋協調性を養うことです。低速で回すことで、ペダルストロークの欠点が拡大され、修正すべきポイントが明確になります。この技術は通常のケイデンスでのペダリングにも転用され、全体的な効率が向上します。
プロ選手から学ぶケイデンス戦略
プロのロードレースは、ケイデンス理論が実践される最高峰の舞台です。歴史的な名勝負の中には、ケイデンスの使い方が勝敗を分けた事例が数多く存在します。
ランス・アームストロング対ヤン・ウルリッヒ
2000年代初頭のツール・ド・フランスで繰り広げられた、ランス・アームストロングとヤン・ウルリッヒのライバル関係は、ケイデンス哲学の対決として象徴的でした。
アームストロングは典型的な高ケイデンスライダーであり、山岳ステージでも105~110rpmという驚異的な回転数を維持しました。彼の戦略は、優れた心肺機能(後に違法な血液ドーピングによるものと判明)を活かし、連続的な高ケイデンスアタックでライバルの筋肉を疲弊させるというものでした。
一方、ウルリッヒはパワフルな低ケイデンスライダーで、登坂時も80~90rpm程度の比較的低い回転数で重いギアを回していました。彼の筋力は圧倒的でしたが、アームストロングの連続攻撃に対応するたびに筋肉が消耗し、最終的に脚が売り切れてしまうという展開が繰り返されました。2001年のアルプ・デュエズでの決戦では、アームストロングが一度弱さを装った後、高ケイデンスで爆発的に加速し、重いギアに固定されていたウルリッヒを置き去りにしました。
クリス・フルームの高ケイデンス支配
クリス・フルームは、高ケイデンス戦略をさらに洗練させた選手です。2015年のツール・ド・フランスのラ・ピエール・サン・マルタン峠では、41分間以上にわたって平均97rpmという高ケイデンスを維持し、ライバルたちを圧倒しました。
フルームの特徴は、シッティング(座った状態)での高ケイデンスアタックです。通常、急勾配ではダンシング(立ち漕ぎ)で加速するのが一般的ですが、フルームはシッティングのまま、異常なほど高い回転数でペダルを回し続けます。この戦術は、心肺機能と神経筋制御の極限を示すものであり、筋肉へのダメージを最小限に抑えながら、持続的な高出力を実現しています。
プロペロトンの84~88rpm平衡点
興味深いことに、ツール・ド・フランスのような長時間レースにおいて、ペロトン全体の平均ケイデンスを分析すると、84~88rpmという狭い範囲に収束することが分かっています。
これは、スプリンター、クライマー、オールラウンダーといった異なるタイプの選手たちが、3週間にわたる過酷なレースを生き残るために、経験的に発見した最適解です。この範囲は、代謝効率、筋肉疲労、心肺負荷のすべてにおいて、長期的に持続可能なバランスポイントなのです。一日だけなら極端なケイデンスでも対応できますが、連日の激戦を戦い抜くには、この範囲が最も合理的なのです。
個人の最適ケイデンスを見つける方法
「90rpmが理想」という一般論はあくまで出発点であり、真の最適ケイデンスは個人によって異なります。筋線維の組成比(遅筋と速筋の割合)、心肺機能、筋力、柔軟性、さらには脚の長さなどの生体力学的要因によって、最も効率的なケイデンスは変わります。
ステップ1:ケイデンスセンサーの導入
客観的なデータなくして最適化はあり得ません。サイクルコンピューターやスマートフォンアプリと連動するケイデンスセンサーは、現代のサイクリストにとって必須のツールです。数千円から入手可能であり、投資対効果は非常に高いと言えます。
ステップ2:自然なケイデンスのベースライン測定
風が穏やかな平坦路で、30~60分間、会話ができる程度の楽なペースで走ります。この際、ケイデンスを意識的にコントロールせず、自然に任せます。ライド後にデータを確認し、平均ケイデンスを記録します。これがあなたの現在の「自由選択ケイデンス」です。多くの場合、初心者は65~75rpm、中級者は75~85rpm程度になることが多いでしょう。
ステップ3:異なるケイデンスでの実験
心拍数やパワーメーターがあればそれを、なければ体感の運動強度を一定に保ちながら、異なるケイデンスで5~10分間のインターバルを行います。たとえば、70rpm、80rpm、90rpm、100rpmといった具合です。
各インターバル中、以下の点をチェックします。
- ペダルストロークは滑らかで、リズムが自然に感じられるか
- 呼吸は安定しており、会話やハミングができるか
- 脚は軽く感じられるか、それとも重く詰まった感じがするか
- 上半身や骨盤に無駄な動きや緊張がないか
ステップ4:パターンの発見
数回の実験ライドを経て、データと体感を照らし合わせると、特定の範囲で最も快適でパワーが出ると感じるゾーンが見つかります。多くの人にとって、それは80~95rpmの範囲内に収まるでしょう。これがあなたの「ホームベースケイデンス」となり、長距離の巡航時の基準となります。
ただし、この数値に固執する必要はありません。状況に応じて柔軟に調整することが重要です。
まとめ:ケイデンスマスターへの道
ロードバイクのケイデンスは、単なる数値以上の意味を持っています。それは、身体の生理学的システムをコントロールするための戦略的ツールです。低ケイデンス・高トルクのスタイルは筋骨格系に負荷をかけ、短期的には高速を実現できますが、筋疲労と怪我のリスクが高まります。一方、高ケイデンス・低トルクのスタイルは心肺系に負荷をかけますが、筋肉を温存し、長時間の持久力と戦術的柔軟性を提供します。
科学的には、60rpm付近が最も代謝効率が良いとされていますが、実際の持続可能性を考慮すると、80~100rpmという範囲が筋肉血流の維持と疲労管理の観点から優れています。プロのペロトンが84~88rpmに収束するのは、数十年にわたる実戦経験が生み出した知恵の結晶です。
最も重要なのは、特定のケイデンスに固執するのではなく、幅広いケイデンスレンジを使いこなせる能力を身につけることです。平坦路では85~100rpmで巡航し、登坂では70~85rpmを維持し、スプリントでは100~120rpmまで上げる。このような柔軟性を持つことで、あらゆる状況に対応できる真の実力が養われます。
そのためには、体幹トレーニング、高ケイデンススピンアップ、片足ペダリング、SFRといった体系的なトレーニングを継続することが不可欠です。自分の身体特性を理解し、データを活用しながら、最適なケイデンスプロファイルを構築していくことが、パフォーマンス向上への確実な道となるでしょう。
ケイデンスを科学的に理解し、戦略的に使いこなすことで、あなたのサイクリングは新たな次元へと進化します。それは単なる速さの追求ではなく、身体と対話しながら、持続可能で効率的な、そして何より楽しいライディングを実現する鍵なのです。


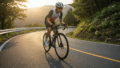

コメント