ロードバイクのパフォーマンスを向上させる要素の中でも、ケイデンス(ペダル回転数)は特に重要な指標として注目されています。サイクリストが直面する永遠のテーマの一つが、最適なケイデンスの選択です。特に70rpmと80rpmという二つの回転数は、多くのライダーが日常的に使用する範囲でありながら、その違いと効果について正確に理解している人は意外と少ないのが現状です。実はこのわずか10rpmの差が、長距離ライドのパフォーマンス、筋肉疲労の蓄積、心肺機能への負荷など、様々な側面で大きな影響を及ぼしています。プロサイクリストが90rpm以上の高回転を維持する一方で、アマチュアライダーの多くが70から80rpmの範囲で走行していることには、明確な理由があります。本記事では、科学的な研究データと実践的な経験を基に、70rpmと80rpmそれぞれの特徴、メリット・デメリット、効果的な使い分け方法について詳しく解説していきます。これらの知識を身につけることで、あなたのライディングがより効率的で快適なものになることでしょう。
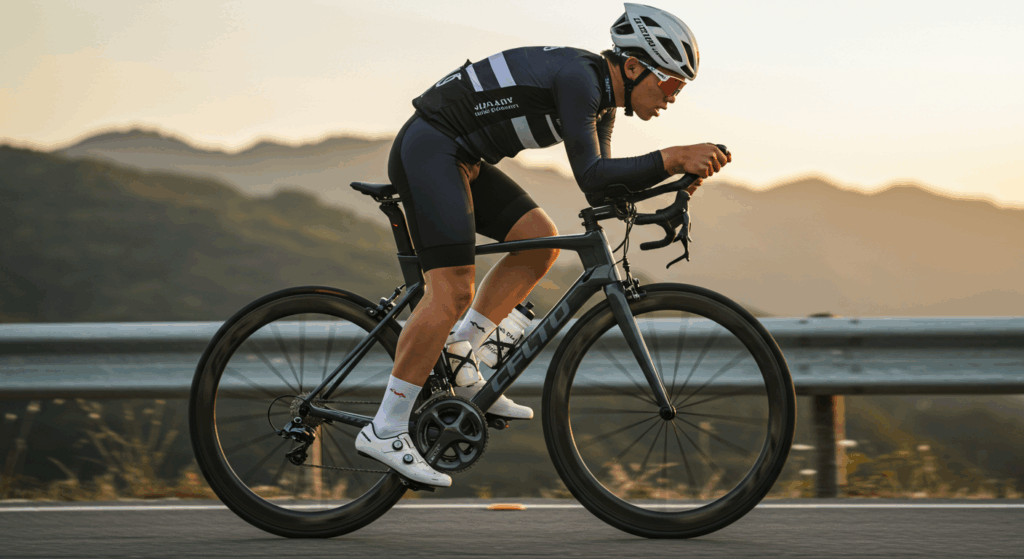
ケイデンスの基本理解と重要性
ケイデンスとは、1分間にペダルを回転させる回数を示す指標であり、rpm(Revolutions Per Minute)という単位で表されます。この数値は単なる回転数以上の意味を持っており、サイクリングにおける効率性、持久力、パフォーマンスを左右する重要な要素となっています。ロードバイクでは一般的に80から100rpmが標準的な範囲とされており、クロスバイクでは60から80rpmが推奨されています。この違いは、車両の特性や走行目的の違いによるものです。
初心者がサイクリングを始める際、多くの場合は60から70rpmという低めのケイデンスから始まることが一般的です。これは、まだペダリング技術が未熟で、高い回転数を維持するための筋肉の協調性が発達していないためです。しかし、経験を積むにつれて、より高いケイデンスでも安定して走れるようになり、最終的には80rpm前後を快適に維持できるようになります。
ケイデンスの選択は、身体への負荷の分配方法を決定する重要な要素です。低いケイデンスでは筋肉への負荷が大きくなり、高いケイデンスでは心肺機能への負荷が増加します。この関係性を理解することで、自分の体力や走行条件に応じて、最適なケイデンスを選択することが可能になります。
70rpmと80rpmの生理学的な違いと身体への影響
酸素消費量の観点から見ると、60から70rpmのケイデンスは最も酸素摂取量が低くなることが科学的研究で明らかになっています。この値は80から100rpmよりも著しく低く、心肺機能への負担が少ないことを意味します。つまり、70rpmで走行する場合、呼吸が楽に感じられ、心拍数の上昇も抑えられるという特徴があります。
一方で、筋電図による研究では興味深い結果が得られています。70rpmや100rpmと比較して、80から90rpmで筋電図の活動が最も低くなることが示されており、この範囲では筋肉への負担が最小化されることが分かっています。この現象は、80rpm付近が人体の筋肉と神経系にとって最も効率的な動作範囲であることを示唆しています。
50rpm程度の極端に低いケイデンスでは、確かに呼吸は楽になりますが、筋肉への負担が過度に大きくなります。各ペダルストロークで大きな力を発揮する必要があるため、筋繊維の損傷が起こりやすく、疲労の蓄積も早まります。逆に100rpmを超える高いケイデンスでは、筋肉の負担は軽減されますが、心拍数が急激に上昇し、呼吸が苦しくなる傾向があります。
ケイデンスが低い場合の筋肉疲労のメカニズムを詳しく見ると、主に速筋繊維が動員されることが分かっています。速筋繊維は瞬発的な力を発揮できる反面、エネルギー消費が早く、乳酸の蓄積も起こりやすいという特徴があります。特に長距離ライドでは、この筋肉疲労の蓄積が後半のパフォーマンスに大きく影響し、ペースダウンの原因となることが多いのです。
70rpmの特徴とメリット・デメリット
70rpmというケイデンスは、多くのサイクリストにとって自然に選択される回転数です。この回転数の最大のメリットは、酸素消費量が少なく、心肺機能への負担が軽いことです。実際の走行では、呼吸が楽に感じられ、会話をしながらでも走行できるレベルの運動強度を維持しやすいという特徴があります。
ドイツの研究機関が行った詳細な分析によると、パワー出力に応じた最適ケイデンスが存在することが明らかになっています。50Wの低出力では40rpm、100Wの中程度の出力では60rpm、200Wの高出力では70rpmが最も効率的とされています。このデータから、70rpmは中から高程度のパワー出力に適したケイデンスであることが分かります。
高強度の運動、例えばFTP(機能的作業閾値パワー)走行やヒルクライムでは、70rpm以上が効率的とされています。70rpmはこの境界に位置しており、パワーを要する場面でも対応可能な回転数です。特にヒルクライムにおいては、斜度が増すにつれてケイデンスが自然に低下する傾向がありますが、70rpmを維持できれば、効率的な登坂が可能になります。
しかしながら、70rpmには明確なデメリットも存在します。最も顕著な問題は、筋肉への負担が80rpmよりも大きくなるという点です。同じ速度で走行する場合、70rpmでは重いギアを使用することになり、1回転あたりのペダルにかかる力が大きくなります。この結果、大腿四頭筋やハムストリングスなどの主要な筋群に大きな負荷がかかり、長距離走行では筋肉疲労の蓄積が顕著になる可能性があります。
また、70rpmでの走行は、膝関節への負担も大きくなります。各ペダルストロークで大きな力を発揮する必要があるため、膝の靭帯や軟骨にストレスがかかりやすくなります。特に膝に既往症がある方や、長時間のライドを行う場合には、この点に注意が必要です。
80rpmの特徴とメリット・デメリット
80rpmは、多くのサイクリング指導書やトレーニングプログラムで推奨される標準的なケイデンスです。この回転数の最大の利点は、筋肉疲労の進行が遅いことです。筋電図研究では、80から90rpmの範囲で筋肉活動が最も効率的になることが繰り返し示されており、これは長距離走行において極めて重要な特性となります。
実際の走行体験から、70rpmと80rpmを同じ速度で比較すると、80rpmでは軽いリアギア、つまり1段軽いギアを使用できることが報告されています。これにより、1回転あたりのパワー負荷が減少し、筋肉への瞬間的な負担が軽減されます。この差は短距離では小さく感じられるかもしれませんが、100kmを超える長距離ライドでは顕著な違いとして現れます。
80rpmでの走行では、遅筋繊維が主に動員されます。遅筋繊維は持久力に優れ、エネルギー効率が良く、乳酸の蓄積も少ないという特徴があります。これにより、長時間の走行でも安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。また、回転運動がスムーズになることで、ペダリング効率も向上し、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。
多くのサイクリストが80rpm付近のケイデンスを好む理由は、酸素消費量よりも筋肉疲労の感覚を優先してケイデンスを調整するためです。実際の走行では、息が少し上がったとしても、筋肉が楽な状態の方が総合的なパフォーマンスが高まることが経験的に知られています。特にグループライドでは、80rpm前後で走ることで、他のライダーとペースを合わせやすくなるという利点もあります。
しかし、80rpmにもデメリットは存在します。最も顕著なのは、70rpmと比較して酸素消費量が多くなり、心拍数が上昇しやすいという点です。心肺機能に制限がある場合や、非常に長時間の低強度走行では、呼吸の負担が気になる可能性があります。また、高いケイデンスを維持するためには、ある程度のペダリング技術が必要であり、初心者にとっては習得に時間がかかる場合があります。
実践的な使い分けと走行条件への対応
走行条件や目的に応じて、70rpmと80rpmを適切に使い分けることが、効率的なサイクリングの鍵となります。平坦路での巡航時には、80rpm前後が推奨されます。この回転数では筋肉疲労の進行が遅く、長時間の走行に適しているためです。実際のトレーニングでも、巡航時のケイデンスを80から90rpm前後で走れるようにすることが、多くのコーチによって目標とされています。
ヒルクライムや高強度走行では、状況が異なります。斜度2パーセントの緩やかな勾配では85rpm前後、斜度4パーセントでは80rpm前後、斜度6パーセントでは70rpm前後が現実的な目標となります。斜度8パーセントを超える急勾配では、60rpm前後まで低下することもありますが、できるだけ70rpm以上を維持することで、筋肉への過度な負担を避けることができます。
長距離ライドでは、走行の段階に応じてケイデンスを調整することが有効です。序盤から中盤では80rpmを基本として、体が温まり、リズムに乗れる状態を作ります。後半の疲労時には、状況に応じて少しケイデンスを落として70rpm台で走ることも選択肢となります。ただし、70rpm以下に下がると急激に筋肉への負担が増加するため、できるだけこのラインを下回らないよう注意が必要です。
風の影響も考慮する必要があります。向かい風では、通常よりも1から2段軽いギアを選択し、ケイデンスを維持することが推奨されます。風の抵抗が増える分、重いギアを使用すると筋肉疲労が早まるためです。逆に追い風では、重めのギアでも80rpm前後を維持しやすくなるため、速度を上げるチャンスとなります。
グループライドでは、集団のペースに合わせる必要があるため、個人の最適ケイデンスから外れることがあります。このような場合でも、ギア選択を工夫して、できるだけ70から80rpmの範囲に収めることが重要です。前方のライダーのケイデンスを観察し、それに近い回転数で走ることで、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。
トレーニングによる適応と向上戦略
ケイデンスへの適応は、計画的なトレーニングによって確実に改善できます。低ケイデンスに慣れている人が80rpmで走ると、最初は心拍数が上がりやすく、呼吸も苦しく感じられます。しかし、継続的にトレーニングすることで、高いケイデンスでも効率的に走れるようになります。この適応過程は通常、4から6週間程度で顕著な改善が見られます。
初心者向けのトレーニングアプローチとしては、段階的な進行が重要です。まず60から70回転の範囲でペダリングを行い、この範囲で安定して走れるようになったら、徐々に回転数を上げていきます。週に1回程度、通常よりも5から10rpm高いケイデンスで10分間走る練習を取り入れることで、神経筋系の適応が促進されます。
クルクルLSDと呼ばれるトレーニング方法は、高ケイデンス適応に特に効果的です。軽いギアで90から100rpmの高めのケイデンスを維持しながら、長時間(1から2時間)走行する練習です。この方法により、回転力が向上し、高ケイデンスでの走行が楽になります。心拍数は低から中程度に保ちながら行うため、心肺機能への過度な負担を避けつつ、ペダリング技術を向上させることができます。
筋力トレーニングとの併用も重要な要素です。特に低ケイデンスでの走行能力を向上させるためには、スクワットやレッグプレスなどの筋力トレーニングが効果的です。週2回程度、下半身の筋力トレーニングを行うことで、70rpmでも筋肉疲労を抑えられるようになります。ただし、実際の長距離走行では、筋力よりも回転力と持久力を重視する傾向があることも理解しておく必要があります。
SFR(スローフォースリピティション)トレーニングは、低ケイデンスでの筋力向上に特化した方法です。40から45rpmという非常に低いケイデンスで、2分間の登坂を6セット行います。このトレーニングにより、70rpmでの走行が相対的に楽に感じられるようになります。ただし、膝への負担が大きいため、週1回程度に留め、十分なウォームアップとクールダウンを行うことが不可欠です。
ギア比とケイデンスの最適な関係性
ギア比の理解と適切な選択は、目標とするケイデンスを維持する上で極めて重要です。ギア比は、前の歯数を後ろの歯数で割った値で表され、この数値が小さいほど軽く漕げることを意味します。一番軽いギアがギア比1前後だと、急な坂道でもケイデンスを維持しやすくなります。
同じ速度で走行する場合、80rpmを維持するには70rpmよりも軽いギアを選択する必要があります。具体的には、1段から2段程度軽いギアにシフトすることで、ケイデンスを10rpm程度上げることができます。例えば、フロント50T、リア17Tで70rpmで走行している場合、リア19Tにシフトすることで、同じ速度で80rpm程度の回転数を実現できます。
現代のロードバイクでは、11速や12速のコンポーネントが主流となっており、細かいギア比の調整が可能です。これにより、70rpmと80rpmの中間的なケイデンス(75rpm程度)も容易に実現でき、状況に応じた柔軟な対応が可能になっています。特にカセットスプロケットの歯数構成を工夫することで、自分の走行スタイルに最適なギア比を構築することができます。
ヒルクライムでは、特にギア比の選択が重要になります。斜度6パーセント以上の坂では、ギア比1.5以下、できれば1.2程度の軽いギアを用意しておくと、70rpm程度のケイデンスを維持しやすくなります。フロントインナー34T、リア28T以上の組み合わせが一般的な選択肢ですが、コンパクトクランク(50-34T)とワイドレシオのカセット(11-32Tや11-34T)の組み合わせも人気があります。
ケイデンス測定機器の活用と管理方法
ケイデンスを正確に把握し、管理するためには、適切な測定機器が不可欠です。ケイデンス機能付きのサイクルコンピューターとケイデンスセンサーの組み合わせにより、リアルタイムでペダル回転数を確認できます。最新のセンサーは、Bluetooth LEやANT+などの無線規格に対応しており、スマートフォンアプリとも連携可能です。
現代のサイクルコンピューターは、GPSとケイデンスセンサーを組み合わせることで、走行速度とケイデンスの関係をリアルタイムで表示できます。これにより、最適なギア選択が容易になり、目標とするケイデンスを維持しやすくなります。また、走行データを記録・分析することで、自分の走行パターンや改善点を客観的に把握することができます。
パワーメーターを使用している場合、ケイデンスとパワー出力の関係をより詳細に分析できます。同じパワーを出す際に、70rpmと80rpmでどちらが効率的かを数値で比較することが可能です。一般的に、200W程度の出力では80rpm前後が最も効率的とされていますが、個人差があるため、自分のデータを蓄積して分析することが重要です。
走行後のデータ分析も重要な要素です。特に長距離ライドでは、前半と後半でケイデンスがどう変化するかを確認することで、ペース配分の改善点が見えてきます。後半にケイデンスが大きく低下する場合、前半のペースが速すぎるか、使用しているケイデンスが適切でない可能性があります。理想的には、走行全体を通じて±5rpm程度の範囲でケイデンスを維持できることが目標となります。
ポジショニングとケイデンスの相互関係
サドルの高さは、ケイデンスの維持と効率に大きく影響します。適切なサドル高は、下死点でペダルを踏んだ時に膝が約150度になる位置とされています。この角度により、筋肉が最も効率的に力を発揮でき、70rpmでも80rpmでも快適に走行できます。
サドルが低すぎると、膝への負担が増加し、特に70rpmの低ケイデンスで問題が顕著になります。膝の屈曲角度が大きくなりすぎるため、関節への圧力が増し、長距離走行での痛みの原因となります。また、筋肉の動作範囲が制限されるため、効率的なペダリングが困難になります。
逆にサドルが高すぎると、下死点での力の伝達が不十分になり、80rpmの高ケイデンスを維持しにくくなります。足が完全に伸びきってしまうため、スムーズな回転運動が妨げられ、骨盤が左右に揺れやすくなります。この揺れはエネルギーロスを生み、疲労の原因となります。
クリート位置の調整も、ペダリング効率とケイデンスに密接に関係しています。一般的には、母指球の真下から5mm程度後方にペダル軸が来る位置が推奨されます。前寄りのクリート位置では、ふくらはぎの筋肉を多く使うことになり、80rpm以上の高ケイデンスに適しています。一方、後ろ寄りのクリート位置では、大腿部の筋肉を主に使うため、70rpm前後の安定したケイデンスに向いています。
ハンドルの高さと距離も、ケイデンスの維持に影響します。ハンドルが低く遠い位置にあると、前傾が強くなり、空気抵抗は減少しますが、呼吸が制限される可能性があります。この姿勢は70rpm程度のトルク型ペダリングには適していますが、80rpm以上の高ケイデンスでは呼吸の制約が問題になることがあります。
パワー出力とケイデンスの最適化戦略
パワーメーターを使用した科学的な分析により、ケイデンスとパワー出力の関係が明確になってきています。コンピューター解析によると、最適ケイデンスはパワー出力によって変化し、100Wの出力では57rpm、200Wでは70rpm、300Wでは86rpm、400Wでは99rpmが最も効率的とされています。
これらのデータから、パワー出力が高くなるほど、高いケイデンスが適していることが分かります。しかし、これはあくまで理論値であり、実際の走行では個人差や環境要因を考慮する必要があります。多くのアマチュアサイクリストにとって、200W前後の出力が巡航パワーとなるため、70から80rpmの範囲が現実的な選択となります。
FTP(機能的作業閾値パワー)付近での走行では、個人によって最適なケイデンスが異なります。一般的には、FTPの90から100パーセントの強度では、75から85rpmの範囲が効率的とされています。この強度では、筋肉疲労と心肺負荷のバランスが重要になるため、両者の中間的なケイデンスが選択されることが多いのです。
長時間のFTP走行では、ケイデンスを固定するよりも、5から10rpmの範囲で変化させることが疲労軽減に効果的です。70から80rpmの範囲を行き来することで、使用する筋肉群を分散させ、特定の筋肉への過度な負担を避けることができます。この戦略は、タイムトライアルやロングライドイベントで特に有効です。
専門的なトレーニングメニューの実践
週間トレーニング計画において、ケイデンスの向上を目指す場合、異なるタイプの練習を組み合わせることが効果的です。週1回の高ケイデンストレーニング(90から100rpm)、週1回の低ケイデンス高負荷トレーニング(60から70rpm)、残りは通常のライド(75から85rpm)という構成が、多くのコーチによって推奨されています。
高ケイデンストレーニングの日は、100から110rpmの高回転を30秒から1分間維持し、その後3分程度の回復走行を挟むインターバルトレーニングを行います。これを5から8セット繰り返すことで、神経筋系の適応が促進され、80rpmが非常に楽に感じられるようになります。このトレーニングは、平坦路や緩い下り坂で行うと効果的です。
低ケイデンス高負荷トレーニングでは、60から70rpmの低回転で、通常より重いギアを使用します。これにより筋力が向上し、70rpmでも効率的に走れるようになります。特に坂道を利用したSFRトレーニングは効果的で、5から8パーセントの勾配で、40から50rpmという極めて低い回転数で2分間登坂し、その後軽いギアで回復走行を行います。
月間の目標として、平均ケイデンスを2から3rpm向上させることを設定します。急激な変化は身体への負担が大きいため、段階的な向上を目指すことが重要です。3か月ごとに、異なるケイデンスでのタイムトライアルを実施し、どのケイデンスが最も効率的かを検証します。同じコースを70rpm、80rpm、90rpmで走行し、タイム、平均心拍数、主観的疲労度を比較することで、自分に最適なケイデンスを見つけることができます。
ペダリング技術の向上とケイデンス効率
効率的なペダリングフォームは、ケイデンスの維持と向上に不可欠な要素です。ペダリングは、踏み込み、下死点通過、引き上げ、上死点通過という4つの局面に分けられ、各局面での適切な技術が、全体の効率を大きく左右します。
70rpmと80rpmでは、求められるペダリング技術に違いがあります。70rpmの低めのケイデンスでは、1回転あたりのトルクが大きいため、踏み込み局面でしっかりとパワーを伝達することが重要です。体重を効果的に使い、大腿四頭筋の力を最大限に活用します。この際、上半身を安定させ、無駄な動きを排除することが効率向上の鍵となります。
80rpmでは、よりスムーズで連続的な動作が求められます。力強さよりもリズムと滑らかさを重視し、円を描くようなイメージでペダリングを行います。特に下死点から引き上げへの移行をスムーズに行うことで、デッドポイントを最小化し、効率的な回転を維持できます。足首を柔軟に使い、かかとをやや上げるようにすることで、この移行がスムーズになります。
体幹の強化も、ケイデンス向上には欠かせません。体幹が弱いと、高いケイデンスで上半身がぶれてしまい、エネルギーロスが発生します。プランクや腹筋運動など、週に2から3回、各10分程度の体幹トレーニングを行うことで、安定したペダリングフォームを維持しながら高いケイデンスを実現できます。太ももの付け根に意識を集中させることで、より効率的な回転運動が可能になります。
栄養補給と回復戦略の最適化
70rpmと80rpmでは、エネルギー消費のパターンが異なるため、それぞれに適した栄養補給戦略が必要です。70rpmでは主に筋肉のグリコーゲンを使用する割合が高く、無酸素性代謝の比率が上がります。一方、80rpmでは有酸素代謝の比率が高くなり、脂肪燃焼の効率も向上します。
長距離ライドで80rpmを維持する場合、炭水化物の補給をこまめに行うことが重要です。1時間あたり30から60gの炭水化物を摂取することで、血糖値を安定させ、パフォーマンスの低下を防げます。エネルギージェルやバー、スポーツドリンクなどを活用し、15から20分ごとに少量ずつ補給することが理想的です。
70rpmで走行する場合、筋肉疲労が蓄積しやすいため、BCAA(分岐鎖アミノ酸)などのサプリメントを併用することで、筋肉のダメージを軽減できます。特にロイシン、イソロイシン、バリンの3つのアミノ酸は、筋肉の分解を抑制し、回復を促進する効果があります。走行前後に5から10gのBCAAを摂取することが推奨されています。
回復戦略も、使用したケイデンスによって異なります。高ケイデンス(80rpm以上)でのトレーニング後は、心肺系の疲労が主であるため、十分な睡眠と軽い有酸素運動による積極的回復が効果的です。翌日は軽めのサイクリングやジョギングを30分程度行うことで、血流を促進し、疲労物質の除去を助けます。
低ケイデンス(70rpm前後)でのトレーニング後は、筋肉のダメージが大きいため、ストレッチやマッサージ、フォームローラーを使用した筋膜リリースが推奨されます。また、トレーニング後30分以内に20から30gのタンパク質を摂取することで、筋肉の修復と成長が促進されます。
競技レベルでの戦略的活用
競技志向のサイクリストにとって、70rpmと80rpmの使い分けは戦術的な要素となります。レースでは、状況に応じて素早くケイデンスを変化させる能力が求められます。アタックの際には100rpm以上の高回転で瞬発的なパワーを発揮し、回復時には70rpm前後で筋肉を休ませるという使い分けが必要です。
ロードレースでは、集団内での位置取りによってもケイデンスを調整する必要があります。集団の前方では風の影響を受けやすいため、80rpm前後の効率的なケイデンスを維持し、エネルギーを温存します。集団後方では、前方のライダーの動きに合わせて頻繁にペースが変化するため、70から90rpmの幅広い範囲で対応できる能力が必要です。
タイムトライアルでは、個人の最も効率的なケイデンスを見極めることが重要です。多くの場合、80から90rpmの範囲に最適値が見つかりますが、コースプロファイルによって調整が必要です。平坦区間では85から90rpm、登坂区間では75から80rpm、下り区間では70から75rpmというように、区間ごとに最適なケイデンスを設定します。
ヒルクライムレースでは、ペース配分とケイデンス管理が勝敗を分けます。序盤は80rpm前後で入り、徐々に斜度が増すにつれて75rpm、70rpmと調整していきます。最後のスパート区間では、残された筋力を最大限に活用するため、65から70rpmの低ケイデンスで大きなトルクを発揮することもあります。
年齢と体力レベルに応じた調整
年齢によって、最適なケイデンスは変化します。若年層(20から30代)のサイクリストは、心肺機能が優れているため、80から90rpmの高めのケイデンスに適応しやすい傾向があります。筋肉の回復も早いため、様々なケイデンスでのトレーニングを積極的に取り入れることができます。
中年層(40から50代)では、筋力は維持されているものの、心肺機能がやや低下し始めるため、75から80rpmの中間的なケイデンスが快適に感じられることが多いです。この年代では、無理に高いケイデンスを追求するよりも、自分にとって最も効率的な範囲を見つけることが重要です。
高年層(60代以上)のサイクリストは、関節への負担を考慮し、70から75rpmのやや低めのケイデンスを選択することが推奨されます。ただし、定期的なトレーニングによって、80rpm程度まで快適に走れる能力を維持することは十分可能です。重要なのは、急激な変化を避け、段階的に適応していくことです。
初心者と上級者でも、アプローチは異なります。初心者は、まず70rpm前後で安定したペダリングができることを目標とし、徐々に80rpmへと移行していきます。この過程で、正しいペダリングフォームを身につけることが最優先です。上級者は、60から100rpmという幅広い範囲で効率的に走れる能力を養い、状況に応じて最適なケイデンスを選択できることを目指します。
まとめと今後の展望
70rpmと80rpmという二つのケイデンスには、それぞれ明確な特徴とメリット・デメリットがあることが理解できました。70rpmは心肺機能への負担が少なく、酸素消費量を抑えられる反面、筋肉への負荷が大きくなります。80rpmは筋肉疲労の進行が遅く、長距離走行に適している反面、心拍数が上昇しやすいという特徴があります。
最適なケイデンスは、個人の体力レベル、走行目的、コース特性、気象条件など、様々な要因によって変化します。重要なのは、両方のケイデンスに対応できる能力を養い、状況に応じて使い分けることです。継続的なトレーニングと適切な機材選択により、70から80rpmの範囲で効率的に走れるようになることは、すべてのサイクリストにとって達成可能な目標です。
今後のサイクリング技術の発展により、ケイデンスの最適化はさらに進化していくでしょう。パワーメーターやスマートトレーナーの普及により、個人に最適なケイデンスをより科学的に分析できるようになっています。また、電動変速システムの進化により、より細かいギア比の調整が可能になり、理想的なケイデンスの維持が容易になっていくと予想されます。
最終的に、70rpmと80rpmのどちらが優れているかという問いに対する答えは、「状況による」ということになります。両方の特性を理解し、自分の体と対話しながら、その時々で最適な選択をすることが、サイクリングを長く楽しむための鍵となるでしょう。データや理論は重要な指針となりますが、最も大切なのは、自分自身の感覚を信じ、楽しみながら走り続けることです。


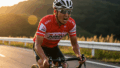

コメント