東京都の自転車政策は、近年大きな転換期を迎えています。令和3年(2021年)5月に改定された「東京都自転車活用推進計画」は、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化に対応するとともに、令和7年度(2025年度)に向けた具体的な目標達成に向けて着実に歩みを進めてきました。この計画は国の第2次自転車活用推進計画と連動しており、環境負荷の少ない持続可能な都市交通の実現、交通安全の向上、健康増進といった複合的な目的を持っています。2025年という節目の年を前に実施された中間見直しでは、これまでの成果を検証しながら、新たに浮上してきた課題への対応策が盛り込まれました。特に注目されるのは、自転車利用者の安全確保に向けた規制強化、自転車通行空間の計画的な整備推進、シェアサイクル事業の広域連携、そして画期的な交通違反取締制度の導入といった具体的な施策です。これらの変更点は、東京都における自転車利用環境を根本から改善し、誰もが安全で快適に自転車を活用できる社会の実現を目指しています。

東京都自転車活用推進計画の基本的な枠組みと改定の経緯
東京都自転車活用推進計画は、平成31年(2019年)3月の初版策定から数えて、令和3年(2021年)5月に大規模な改定が行われました。この改定の最も重要な背景となったのは、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大でした。通勤・通学における密を避けた移動手段として自転車が再評価され、利用者が急増したことで、自転車インフラの整備や安全対策の重要性が一層高まりました。
改定計画では、地域特性に応じた重点的な取り組みを実施するため、優先地区の設定が行われました。新宿地区、吉祥寺・三鷹・武蔵境地区、晴海・豊洲・有明地区という3つの地区が選定され、それぞれ商業集積地、住宅地、新開発地域という異なる特性を持つエリアで集中的な施策展開が図られることとなりました。この地区別アプローチにより、画一的な施策ではなく、地域の実情に即したきめ細かな対応が可能になっています。
計画期間は国の第2次自転車活用推進計画と同様に令和7年度(2025年度)までとされており、計画開始から数年が経過した現在、各種施策の進捗状況を検証し、必要な修正を加える中間見直しの段階に入っています。この見直しでは、当初想定していた以上に進展した分野と、新たに顕在化した課題の両方に対応することが求められています。
主要変更点:安全利用に関する規制強化と保険義務化
東京都における自転車政策の中間見直しで最も重視されたのが、安全利用の促進です。令和2年(2020年)4月1日から施行された「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。この義務は自転車利用者本人だけでなく、未成年者の保護者、さらには業務で従業員に自転車を使用させる事業者にまで及んでいます。
保険加入義務化の背景には、自転車事故による高額賠償事例の増加があります。神戸地裁で下された判決では、当時11歳の男児が起こした自転車事故に対して約9500万円という極めて高額な損害賠償命令が出されました。このような事例は全国的に複数報告されており、被害者救済と加害者の経済的破綻を防ぐという両面から、保険加入の必要性が強く認識されるようになりました。
対象となる保険は、自転車保険という名称のものに限られません。自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として付帯されている個人賠償責任補償、あるいはクレジットカードに自動付帯している個人賠償責任保険など、幅広い保険商品が要件を満たします。既に加入している保険で要件を満たしている場合も多いため、まずは自身の保険契約内容を確認することが推奨されています。
さらに、令和5年(2023年)4月1日からは、道路交通法の改正により、すべての年齢の自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務化されました。東京都では、これに先立つ平成25年(2013年)7月1日から、児童及び幼児の保護者に対してヘルメット着用を促す条例が制定されていましたが、国の法改正により対象が全年齢に拡大されたことで、都の施策も強化されました。
警視庁のデータによると、自転車乗用中の事故で死亡した人のうち64.9パーセントが頭部損傷を致命傷としており、ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比較して約2.7倍高いという科学的なエビデンスが示されています。このデータを踏まえ、東京都教育委員会は令和6年度(2024年度)から、すべての都立学校において自転車通学時のヘルメット着用を必須とする方針を打ち出しました。努力義務ではなく実質的な義務とすることで、若年層の安全意識向上と事故防止を図っています。
主要変更点:自転車通行空間の計画的整備とネットワーク化
自転車の安全な通行環境を確保するため、東京都建設局は「東京都自転車通行空間整備推進計画」を策定し、2040年代に向けた長期的なビジョンを提示しています。中間見直しでは、この長期計画の中で優先整備区間を明確化し、限られた予算と時間の中で最大の効果を上げるための戦略的なアプローチが採用されました。
令和6年(2024年)2月6日には「自転車通行空間ネットワーク計画調整会議」が開催され、東京都、警察庁、各区市町村の担当者が一堂に会して、自転車通行空間の整備について綿密な調整が行われました。この会議の重要性は、国道、都道、区道という管理主体の異なる道路を連続的なネットワークとして整備するために、関係機関の連携が不可欠である点にあります。
国土交通省東京国道事務所も、東京23区内における直轄国道の自転車通行空間整備計画を公表しており、令和6年(2024年)3月末時点での整備状況がGISデータとともに提供されています。都道についても、令和4年度(2022年度)末時点での整備状況が東京都都市整備局から公表されており、着実に整備延長が伸びていることが数値で確認できます。
自転車通行空間の整備形態は、道路の条件に応じて柔軟に選択されています。物理的に分離された自転車道、路面標示による自転車専用通行帯、そして車道混在形式など、道路の幅員や交通量、地域の特性を考慮して最適な形態が採用されます。特に幹線道路においては、青色の路面標示や矢羽根マークといった視覚的に明確な誘導により、自転車と自動車の通行空間を区分することで、双方の安全性向上が図られています。
整備計画の優先順位付けにおいては、駅周辺や商業地域など自転車利用が多い地域が重点的に選定されています。加えて、学校や公園といった市民の日常的な利用が多い施設へのアクセス路も優先的な整備対象となっており、生活に密着した実用的なネットワーク構築が目指されています。観光地やサイクリングルートとして魅力的な河川敷道路なども整備対象に含まれ、レクリエーション需要にも対応した多面的なアプローチが取られています。
主要変更点:シェアサイクル事業の広域連携強化
東京都環境局が令和3年(2021年)の計画改定で掲げた「利用エリアの広域化に向けた事業者間の連携の推進」は、中間見直しの段階で具体的な成果を生み出しています。令和3年(2021年)11月から西新宿地域で、令和4年(2022年)12月から池袋地域で開始されたポート用地共同利用検証事業は、この方針を具現化した先進的な取り組みです。
この事業の画期的な点は、複数のシェアサイクル事業者が同一のポート(自転車ステーション)を共同で利用できるようにしたことです。従来は事業者ごとに異なるポートを設置していたため、利用者は自分が契約している事業者のポートでしか自転車を借りたり返却したりできず、利便性が大きく制限されていました。また、限られた公共空間に複数事業者が重複してポートを設置することによる非効率性も課題として指摘されていました。
令和6年(2024年)3月末時点で、全国のシェアサイクルポート数は20,000箇所を超え、利用者数も年々増加の一途をたどっています。東京都内では、千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区をはじめとする多くの区で、区境を越えて相互利用が可能な広域シェアサイクルシステムが導入されており、シームレスな移動環境が実現しつつあります。
シェアサイクルは、鉄道駅と最終目的地を結ぶラストワンマイルの移動手段として特に注目されています。新型コロナウイルス感染症の拡大以降、公共交通機関の密を避けた移動手段として利用が急増し、その利便性が広く認識されるようになりました。通勤・通学での定期的な利用だけでなく、観光や買い物といった多様な用途で活用されており、都市の新たな移動インフラとして定着しています。
東京都は民間事業者との連携を一層強化し、公有地の活用促進やポート設置に関する規制緩和などを通じて、シェアサイクル事業の拡大を積極的に支援しています。電動アシスト自転車の導入促進により、坂道の多い地域でも利用しやすい環境が整えられており、利用者層の拡大にも寄与しています。
主要変更点:放置自転車対策の成果と目標前倒し達成
東京都生活文化スポーツ局の調査によると、令和6年度(2024年度)の駅前放置自転車数は14,876台となり、「東京都自転車安全利用推進計画」で令和7年度(2025年度)の目標として設定していた15,000台を1年前倒しで達成しました。これは、数十年にわたる継続的な対策が実を結んだ成果といえます。
放置自転車問題は昭和40年代から深刻な社会問題として認識され、平成2年(1990年)には約243,000台とピークに達しました。その後、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」の継続的な実施(令和6年度で42回目)、自転車等放置禁止区域の設定、駐輪場の計画的な整備、警告なしでの即時撤去の実施など、総合的かつ多角的な対策により、着実な減少が実現してきました。
しかし、放置自転車対策には依然として大きな行政コストが投じられています。令和4年度(2022年度)には、駐輪場整備に約22億9千万円、放置自転車の撤去・保管に約49億2千万円という巨額の予算が使われています。放置自転車が歩行者や緊急車両の通行を妨げ、街の景観を損ない、場合によっては犯罪の温床となるリスクを考えれば、この投資は必要不可欠なものです。
各区市町村では、主要駅周辺を「放置禁止区域」に指定し、警告を経ずに即時撤去を行う厳格な運用を実施しています。撤去された自転車は指定の保管場所に移送され、所有者に返還される際には撤去・保管料の支払いが必要となります。中央区、新宿区、世田谷区、荒川区など、都内の多くの自治体がこの制度を運用しており、放置自転車の抑止効果を上げています。
駐輪場の整備も放置自転車対策の重要な柱です。民間事業者による駐輪場整備を促進するための補助金制度や、建築基準法に基づく駐輪場設置義務の強化など、多様な施策が展開されています。近年では、機械式駐輪場の導入が進み、限られた土地でより多くの自転車を収容できるようになったことで、駅前の貴重な空間を有効活用する取り組みが広がっています。
令和6年度(2024年度)から令和7年度(2025年度)にかけての「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」では、「自転車の 代わりに置こう 思いやり」をスローガンに掲げ、単なる取り締まりや撤去だけでなく、利用者一人ひとりのモラル向上を促すソフト面の啓発活動にも力が入れられています。
主要変更点:画期的な交通違反取締制度の導入
東京都自転車活用推進計画の中間見直しにおいて、最も注目される変更点の一つが、自転車利用者の交通ルール遵守を促進するための新たな制度導入です。令和6年(2024年)11月1日から、自転車のながら運転と飲酒運転に対する罰則が大幅に強化されました。スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視しながら走行する行為には、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるようになりました。飲酒運転については、さらに厳しい1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が設けられています。
そして、さらに画期的な制度改正として、令和8年(2026年)4月1日から、自転車の交通違反に対して青切符(交通反則通告制度)が導入される予定です。これは自転車の交通安全対策において歴史的な転換点となる制度変更といえます。対象となるのは16歳以上の自転車利用者で、信号無視、一時不停止、携帯電話使用、傘やイヤホン使用での走行、ブレーキ不良自転車の運転、遮断踏切への立ち入り、通行禁止区域の走行、逆走、歩道での徐行違反など、合計113種類の違反行為が対象とされています。
青切符が交付されると反則金の納付が求められ、納付すれば刑事責任は問われませんが、納付しない場合には刑事手続きに移行することになります。ただし、すべての違反に対して機械的に青切符が適用されるわけではなく、「交通事故に直結するような危険な行為」や「警察の指導警告に従わず違反を繰り返した場合」に重点的に取り締まりが行われる方針が示されています。
令和6年(2024年)の統計によると、全国の自転車関連事故は67,531件で、全交通事故の23.2パーセントを占めています。東京都においては、令和5年(2023年)中の自転車交通事故件数が14,525件で、全交通事故に占める割合が46.3パーセントに達しており、自転車事故対策の重要性は極めて高い状況にあります。青切符制度の導入により、自転車利用者の交通ルール遵守意識が向上し、事故減少につながることが強く期待されています。
警視庁では「自転車安全利用五則」の周知徹底にも力を入れています。車道が原則で左側を通行すること、歩道は例外であり歩行者を優先すること、交差点では信号と一時停止を守って安全確認すること、夜間はライトを点灯すること、飲酒運転は禁止であること、ヘルメットを着用すること、という基本的なルールの浸透が図られています。
主要変更点:サイクルツーリズムと健康・環境面での推進強化
国の第2次自転車活用推進計画では、「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」が重要目標の一つとして掲げられており、東京都もこの方針に沿った施策を展開しています。東京都内には、荒川や多摩川沿いのサイクリングロード、皇居周辺の人気サイクリングコース、奥多摩や檜原村などの山間部の魅力的なルートなど、多様なサイクリング環境が存在します。
令和2年(2020年)に開催された東京オリンピック・パラリンピックの自転車競技は、都内のサイクリング環境整備を加速させる契機となりました。競技会場周辺だけでなく、都内全域でサイクリストの受け入れ体制が強化され、案内標識の多言語化、サイクルステーションの設置、自転車持ち込み可能な宿泊施設の増加などが進みました。
東京都は「TOKYO自転車ナビ」というウェブサイトを開設し、おすすめのサイクリングコース、レンタサイクル情報、駐輪場マップ、自転車イベント情報などを総合的に発信しています。また、「東京自転車活用推進パートナー」という枠組みを設け、自転車の活用に積極的に取り組む企業や団体との連携を強化し、官民一体となった自転車活用の推進を図っています。
環境面では、自転車は脱炭素社会の実現に大きく貢献する交通手段として位置づけられています。自動車からの転換により、CO2排出量の削減、大気汚染の改善、騒音の低減などの複合的な効果が期待されます。東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」においても、自転車利用の促進が重要な施策の一つとして明記されており、持続可能な都市交通システムの構築に向けた取り組みが進められています。
健康増進の観点からも、自転車利用は積極的に推奨されています。日常的な自転車利用により、適度な有酸素運動を継続的に行うことができ、生活習慣病の予防、メンタルヘルスの改善、体力維持などの多面的な効果が得られます。東京都では「TOKYO HEALTH ACTION」の一環として、日常生活における身体活動の増加を促しており、自転車利用もその重要な手段の一つとされています。
企業における自転車通勤推進も、中間見直しで強化された施策の一つです。国土交通省は「自転車通勤推進企業宣言プロジェクト」を創設し、自転車通勤を推進する企業や団体を認証する制度を設けています。「宣言企業」として認証されるには、従業員用の駐輪場の確保、年1回以上の交通安全教育の実施、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化という3つの要件を満たす必要があります。令和5年(2023年)4月1日時点で、「宣言企業」として56社、より高度な取り組みを実施する「優良企業」として6社が認証されており、企業の自転車通勤支援の動きが広がっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通勤時の密を避ける手段として自転車通勤が注目され、多くの企業が制度導入や支援拡充に乗り出しました。この傾向は感染症の収束後も継続しており、新しいワークスタイルの一つとして定着しつつあります。
2025年度以降の展望と残された課題
令和7年度(2025年度)は、国の第2次自転車活用推進計画の最終年度であり、東京都の計画も一定の節目を迎えます。これまでの取り組みにより、自転車通行空間の整備延長の増加、シェアサイクルの利用拡大、放置自転車数の大幅な減少など、数値目標の達成状況は概ね良好です。しかし、依然として解決すべき課題も多く残されています。
第一の課題は、自転車事故の減少が十分に進んでいないことです。自転車関連事故の割合は依然として高く、特に東京都では全交通事故の半数近くを占める状況が続いています。ヘルメット着用率の向上、交通ルール遵守の徹底、自転車利用者と歩行者・自動車ドライバーとの相互理解促進など、総合的な安全対策の一層の強化が求められています。
第二の課題は、自転車通行空間の整備が進んでいるものの、まだ不十分な地域が多く存在することです。幹線道路における整備は比較的進んでいますが、生活道路における安全な通行環境の確保は大きな課題として残されています。地域の実情に応じたきめ細かな整備計画の策定と実行が必要です。
第三の課題は、駐輪場不足の問題です。放置自転車数は大幅に減少しましたが、依然として多くの駅周辺で駐輪需要に対して供給が追いついていない状況があります。特に朝の通勤・通学時間帯には駐輪場が満車となり、やむを得ず路上に駐輪するケースが見られます。民間事業者との連携強化、既存施設の有効活用、機械式駐輪場の導入拡大などにより、駐輪需要に適切に対応する必要があります。
第四の課題は、電動キックボードなど新たなモビリティの普及に伴う交通環境の変化への対応です。令和5年(2023年)7月の改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車という新たな区分が創設され、一定の基準を満たす電動キックボードは16歳以上であれば免許なしで公道を走行できるようになりました。これらのモビリティは自転車と同様の交通空間を利用するため、ルールの周知、安全対策の強化、インフラ整備などが求められています。
第五の課題は、地域間格差の問題です。都心部では自転車インフラが比較的整備されている一方、多摩地域や島しょ部では遅れている地域もあります。地域の特性に応じた施策の展開と、全都的な底上げが必要です。
令和7年度(2025年度)を迎えるにあたり、これまでの取り組みの成果を客観的に検証し、新たな課題に対応するための次期計画の策定が重要な局面を迎えています。自転車は環境にやさしく、健康増進にもつながり、都市の活力を高める重要な交通手段です。東京都自転車活用推進計画の中間見直しで示された主要変更点を着実に実行し、さらに社会情勢の変化や技術革新に柔軟に対応しながら、誰もが安全で快適に自転車を利用できる東京の実現に向けた取り組みが継続されることが期待されています。



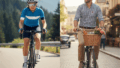
コメント